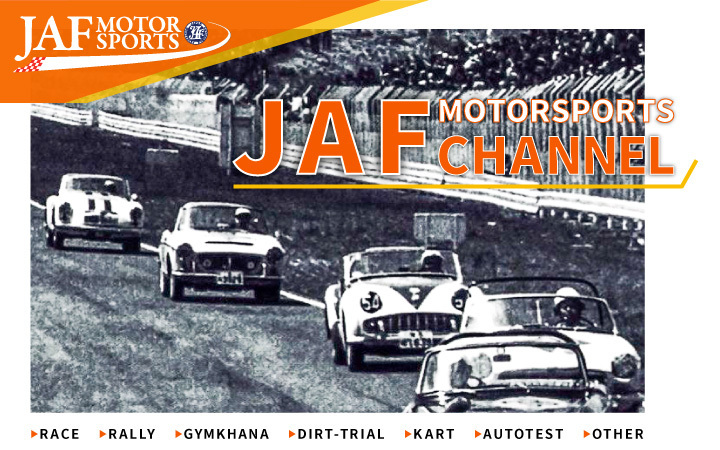これは果たしてデモランなのか!? 往年の名車が真剣勝負! 『マスターズF1』の濃い中身
2019年1月21日
マスターズ・ヒストリック・フォーミュラ・ワン
JAF公認レース初開催・鈴鹿インサイドレポート

「鈴鹿サウンド・オブ・エンジン2017」で日本に初上陸した「マスターズ・ヒストリック・フォーミュラ・ワン」が、2018年は公認レースとして帰ってきた。ここでは名車と共に海を渡ってきた参加選手たちの、ヒストリックF1に馳せる様々な思いを詳報する。
MASTERS HISTORIC FORMULA ONE CHAMPIONSHIP(Masters USA)
RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE 2018
開催日:2018年11月17〜18日 開催地:鈴鹿サーキット
主催:SMSC、(株)モビリティランド
フォト/吉見幸夫、JAFスポーツ編集部 レポート/深澤誠人、JAFスポーツ編集部



クラシックF1マシンがレースをする。それも、FIA公認のチャンピオンシップという冠を得てシリーズを戦うと聞いて、皆さんはどう感じるだろうか。
2017年秋、三重県の鈴鹿サーキットに突如現れた「マスターズ・ヒストリック・フォーミュラ・ワン(以下マスターズF1)」。 日本初上陸となった2017年は、あくまで模擬レースという扱いだった。しかし、ヒストリックF1マシンが本気としか見えないバトルを繰り広げた姿は、日本のコアなレースファンの度肝を抜いたことは記憶に新しい。
2018年11月17〜18日に「鈴鹿サウンド・オブ・エンジン2018」で再上陸を果たしたマスターズF1は、日本では初となるJAF公認のタイトルを得て開催された。 幸運にも、その姿を鈴鹿の観客席で目の当たりにした人は、彼らの繰り出す走りの「本気度」に衝撃を受けたのではないだろうか。その台数たるや20台オーバー。 コスワースDFVを搭載する歴史的なF1マシンが手加減なしの全開走行に挑み、サイド・バイ・サイド、テール・トゥ・ノーズは当たり前。 もちろんオーバーテイクもコース各所で行われた。
貴重な当時モノのF1マシンだけに、「デモラン」にしては激しすぎる。一体、このレースは何なのか……? グランドスタンドで観ているだけでは分からない、この奥深きマスターズF1の詳細を、鈴鹿を訪れた参加選手のコメントを元に紹介していこう。
「マスターズF1」シリーズは欧州と北米で開催中
「Masters Historic Formula One」は、欧州を中心に開催されているヒストリックF1を使ったレースシリーズで、2013年にFIA公認となり、FIAのヒストリック選手権としてシリーズ開催されている(この欧州シリーズは2019年も7戦開催を予定)。 北米でも同様のシリーズが開催されているが、こちらはFIAのチャンピオンシップはかけられておらず、今回鈴鹿で行われた2018年大会は、この「Masters USA」シリーズの一環として、JAF公認レース(予選及びレース1&レース2)が開催された。
このマスターズF1では、F1世界選手権を彩った往年の名車たちがパドックに溢れるというファン垂涎の貴重な機会となっているのだが、参加車両は、1966〜1985年までの3.0L自然吸気エンジンを搭載するF1車両、というのが基本となっている。
>
そこに製作年度とグランド・エフェクトの有無によって「スチュワート・クラス」、「フィッティパルディ・クラス」、「ヘッド・クラス」、「ラウダ・クラス」というクラス区分がなされており、1978年を境界とした「フィッティパルディ&スチュワート・クラス」と「ヘッド&ラウダ・クラス」の2クラスでレースが行われている。
そして参加車両は、FIAが定める「ヒストリック・テクニカル・パスポート」を満たす必要があり、それらはロールバーや燃料タンク、シートベルトといった安全装備の装着と、モノコックのクラックテストで構成されている。
中でも、ロールバーはオリジナルよりも遥かに高い位置まで延長されているため、車両の姿は当時とはこの点で明確に異なっている。また、クラック(亀裂)テストへの対応として、アルミモノコックのパネルが更新されることもあるため、厳密な意味では、オリジナルの車両とは異なるものと言える。
現在のところ、搭載エンジンは事実上コスワースDFVのワンメイクとなっており、コストキャップとパフォーマンスの平準化のほか、旧いエンジンと車体の保護という意味もあり、回転数は10,000回転までとリミットされ、マイレージも規則で管理されている。
DFVワンメイクではあるが、パドックを眺めると、車体とエンジンの時代や世代が合致したマシンはかなり珍しく、そのほとんどがエンジンビルダーによるオーバーホールやリビルドした個体を搭載しており、F3000時代に供給されたヘッドカバーが目立っていた。
マスターズF1では、このように車体やエンジンとも、オリジナリティという部分に関しては極めてラジカルに維持・管理されているのが実態だ。そういった意味で、マスターズF1の参加車両は、歴史的なマシンの動態保存を目的としているだけではない。
つまり、現代の安全基準を満たしたヒストリックという枠組みの中で、たゆまぬ進化を続けて次世代へ継承されてゆく、『現在を生きるレーシングカー』だと言えるだろう。
DFVの咆哮を背負い、驚愕の速度域で駆ける
鈴鹿サーキットで、DFVエンジンが奏でる音を実際に味わった人ならば理解できるだろう。旧い設計のエンジンだけが持つ、空気そのものを叩きつける、容赦のない太いサウンドは、日本ではもう味わえなくなったものだ。これらのDFVエンジンがパワーを絞っていない証拠に、音のヌケや空回り感は一切感じなかった。
このエンジンを掛け値なしに10,000回転まで引っ張ると、バックストレートでも最高速270km/hにまで到達し、ラップタイムは予選で1分56秒台を記録してみせた。
しかも、ドライバー曰く「まだポケットにタイムはあるよ、1.5秒くらい(笑)」というレベルでの走り。ちなみに、鈴鹿のラップレコードは、F3マシンで1分50秒台、GT300で1分55秒台だ。マスターズF1のモノコックは基本的にアルミで、タイヤはバイアスというネガティブ要素を勘案すると、このタイムの凄まじさが浮き彫りになる。
マスターズF1の参戦車両が装着するタイヤは、AVON(エイボン)社からワンメイク供給され、タイヤはバイアス構造の1コンパウンド。ドライ用(エイボンA11)とウェット用(エイボンA15)タイヤが用意されているが、サイズ以外は全車同じスペックだ。
S字コーナーやスプーンカーブを、大きなスラストアングルで駆け抜ける様は、現代のフォーミュラでは見られないもので、ドライバーとマシンの格闘が見て取れるはずだ。
そして、そんなドライバーたちのほとんどは、「オーナードライバー」なのだ。
歴史的な個体のオーナーとして、そして、決して遊びでは済まされない速度域を走るドライバーとして、なぜ旧いF1マシンを選び、このステージで走っているのか。そして、維持や管理はどうなっているのか。この疑問をオーナードライバーたちにぶつけてみた。
マスターズF1で、夢を実現した参加選手たち
F1マシンを選んだ理由については、全員が共通して「子供の頃に見て、憧れていたから」というものだった。マスターズF1のドライバーたちの年齢層は実に幅広く、影響を受けた時期が幼少であったりティーンネイジャーであったりするため、チョイスしたマシンの年代がバラけて、現在のマスターズF1のエントリーリストが出来上がっている。
なぜデモランではなく、本気モードの「レース」に敢えてエントリーするのか。この疑問についても、ほぼ全員が同じ意見を述べていた。
43号車のティレル012を駆るステファン・ロマーク選手曰く「自分はシリアスなレースを望んでる……。ただし、ちょっとだけ手加減した仕様でね。それは、もう二度と作られない、こうしたマシンの歴史的価値は大切だから。このグループ(マスターズF1参加者)はみんな、同じ考えだよ」と、明快かつシンプルに答えてくれた。
維持費について明確に答えてくれるドライバーは少なかったが、プロのメカニックを複数帯同してトップレベルの戦闘力を維持すると「転戦費用込みで年間でゆうに億を超える」という話もあった。
しかし、多くの選手はもっとコンパクトな態勢を採っており、部品も「壊れたら直しましょう」といった緩いもの。こういう態勢なら「欧州F3シリーズに出るより、かなり安く上がると思うよ」とのことだ。上を見ればキリがないのは、どのカテゴリーでも同じだが、いずれにしても、最低でも年間で数千万円は軽く飛んでゆく計算になる。
希少なパーツ群については「壊れたら作ればいいんだよ」と口を揃えているが、DFVエンジンについてはリビルト会社が複数存在するため、「心配ないよ。お財布を気にしなければね!」という意見も。旧いF1マシンの維持については、「手間ヒマかければ問題ない」という考え方が、”マスターズF1コミュニティ”の共通見解のようだ。
そして、多くの選手が、旧いF1マシンを入手した後に長い時間をかけてレストアを施し、自らドライバーとしてのトレーニングを積んで、参戦していることも分かった
若い頃からレースを嗜んでいるベテランだけでなく、F1マシンを入手することを決意してからレース活動を始めた選手もいる。これらレースキャリアが異なる選手たちが、ヒストリックF1マシンを、ほぼ同じペースで走らせている。
このために必要なものは何かと尋ねると、17号車シャドウDN9を駆るチャールズ・ワーナー選手によれば、特別なドライバーとしてのキャリアやスキルではなく、「経験だ。経験を重ねれば、それで大丈夫だ」というコメントをもらった。
こうして見ると、マスターズF1は旧いF1マシンをひけらかす、単なる道楽などではなく、レーシングドライバーとしてレーシングカーを正しく扱える「経験」と「力量」が求められていることが分かる。そして、彼らの言葉の端々には、往時のF1とF1マシンに対する愛情が溢れていることを、インタビューを通じて痛感することができた。
そんな百戦錬磨のアマチュアドライバーたちが、鈴鹿サーキットに対して持った印象は、現役のF1ドライバーたちのコメントとそう変わらないものだった。
2017年に続いて2回目、または今回初めて鈴鹿を走るドライバーたちは、「チャレンジング」、「今じゃもう生まれて来ないオールドスクールな楽しさ」、「音楽のようなリズムのあるコース。曲? Queenの『We are the Champions』さ!」と語ってくれた。
伝統を醸す鈴鹿サーキットと往時のF1マシンの組み合わせ。相性は抜群のようだ。
「マスターズF1」はデモランか? レースか?
製造年によってクラス分けがなされ、車両のオリジナリティを損なうことを厭わず、車両規則に合致させるためモノコックを改修してまでエントリーする。
そして、歴史的なマシンを虐めるような全開走行を、接触やクラッシュのリスクが高い、真剣勝負の「レース」というステージで走らるマスターズF1の参加選手たち。
一方で、歴史を背負ったF1マシンの価値を理解し、自分だけでなく仲間のマシンをも愛するというマインドを持ち、「マシンを次の世代へと継承するのも、自分たちに課せられた使命である」と言い切った選手もいた。そこにあるのは、深い愛情だ。
「レース」のリスクと「ヒストリック」の価値。この相反する要素を、彼らは一体どのように消化しているのか。17号車チャールズ・ワーナー選手の言葉を借りてみよう。
「我々はみんな、デモランではなくレースを望んでいるのだと思う。というのは、人間というのは競争をする生き物なんだ。だから、自分たちはこのマスターズF1を、リアルでハードなレースと、デモランとの間になるように作ってきた。
例えば、こんなルールがある。レース中にクルマが接触したら、『そういうバッドガイは、それでアウト』で、ペナルティを受けるんだ。
そして、我々がとても大事にしているのは、このレースは『マシンがスター(The Car is the star)』であって、ドライバーではないんだよ、ということなんだ」。
世界を股にかける道楽者で、アスリートで、ルールとマナーを守るジェントルメン。そんな紳士たちが作り、楽しみ、守る。そんな古き良き精神が息づくレースなのだ。
日本における2019年のマスターズF1の開催は未定とのことだが、鈴鹿サウンド・オブ・エンジンのメインコンテンツとして3度目の来日を願いたいところだ。
本気のレース・スペックを維持する、本物のF1マシンたちが活き活きと走る。デモンストレーションとは全く異なる、パドックの緊張感と迫力の走りをぜひ体験してほしい。脳を直接揺さぶるDFVサウンドは、決してほかで味わうことができないのだから。








2018年シーズンの「ヘッド&ラウダ・クラス」チャンピオンのニック・パドモア選手。レース1で総合2位入賞後に鈴鹿の印象を聞いた。「アメイジングだよ……。スパ(・フランコルシャン/鈴鹿サーキットと友好協定を締結)よりも速いんじゃないかな。アイルトン・セナが走っているのを見て育ったし、とても歴史のあるコースだから、ずっと鈴鹿を走りたいと思っていたんだ。このコースのポイントは130Rだと思う。鈴鹿はドライバーに覚悟を要求するコースで、リアルに、ル・マンのためのコースだよ。まだ完全には把握してないから、できれば来週もまた来て走りたいくらい、難しい」。パドモア選手にとって初めての鈴鹿だった。


1981年のチャンピオンマシン、ブラバムBT49Cを走らせるホアキン・フォルチ-ルシニョール選手。もともとは他のF1マシンを持っていたが、「バーニー・エクレストン(かつてのブラバムチームのオーナー)が友人なんだけど、なぜブラバムに乗らないんだって言われてね。そりゃ持ってないからだよって言ったら、マシンを貸してくれて。何年か後に自分でこのマシンを手に入れたので、借りてたマシンはバーニーに返したよ」と、サラッと言ってのけた。このマシンで初チャンピオンを獲得したネルソン・ピケとも交友があるそうで、「走っている時は、彼のようにありたいんだけど……いや、さすがに難しいよ」と、大きな目を見開きながら笑っていた。


今回のエントラントで最も旧い1972年のマーチ721Gを走らせるスティーブ・クック選手。「一番旧いんだけど、ストレートスピードは3番手なんだ。このクルマ、ダウンフォースがない分、抵抗も少ないからね」と笑う。その表情は趣味を愛する悪ガキそのもの。鈴鹿については「いや、素晴らしい。楽しいコースですよ、狭く見えて……実際、ホントに狭いんだけど、アップダウンもあって。ダンロップは途中からコースがなくなっちゃうから、ドライバーをだます『悪いコーナー』だね(笑)。デグナーの一つ目は、自宅のガレージに160km/hで飛び込むような感じだよ」とも。「このマシンは4年かけてレストアしたんだ。持ってきた時は、リアセクションには何もなくて、全部作ったんだよ」と、立て板に水の名調子で楽しげに話してくれた。


全参加者の中で、最も態勢を充実させてロータス91を走らせるのは、2018年シリーズ「フィッティパルディ&スチュワート・クラス」チャンピオンのグレゴリー・ソーントン選手。そして、今大会では2レースとも総合優勝を飾り圧倒的な強さを見せた。このレースに情熱を捧げる端緒はティーンネイジャーの頃だそうで、「エリオ・デ・アンジェリスとコーリン・チャップマンがロータス91のホイールに座っている写真があって。「レーシングカーに乗ったらモテる」って当時からの友人に言ってたんだよね」というシンプルなもの。「だって、男子校だったから(笑)」という話も、男の趣味らしくて面白い。彼のロータス91は元々92だったが、これは、そもそも往時のロータスが91から92へとコンバートした車体。それをわざわざ、マスターズF1のレギュレーションに合致させるため、再び91へと戻したといういわくつきのマシンなんだとか。


身長192cmと長身のチャールズ・ワーナー選手も「ティーンネイジャーの頃に見ていたマシン」を入手したという、夢を実現したドライバー。しかし、彼には一つ問題があり、「自分は背が高すぎる。だから、私が乗れるのはこのシャドウDN9Bしかなかった。これは元々大柄なドライバー(ハンス・シュトック)のために設計されているからね。他のマシンなんて、入ることさえできなかったんだから(笑)」と嘆いていた。こうした旧いF1マシンをドライブするにあたっては「特別なキャリアは要らないと思う。ただ、レースカーを運転する経験は積む必要はある。経験すれば大丈夫だ」というが、自身はダットサン・フェアレディの時代からアマチュアレースを嗜んでいたそうで、実は相当手練れたドライバーだ。


2017年はチームーオーナーである父・フランク氏とマシンをシェアして鈴鹿を走ったマイケル・ライアン選手。親子で戦うファミリーチームだけに「ウチがレースファミリーでF1マシンを走らせていたから、このレースに出るのは自然なことだった」と語る。初めてのレースはこのヘスケスで、なんと16歳だったという。マスターズF1では2016年に「フィッティパルディ&スチュワート・クラス」、2017年には「ヘッド&ラウダ・クラス」でタイトルを獲得しており、FIA-GT3やブランパン耐久シリーズでのチャンピオン獲得経験や、ヨーロピアン・ル・マンではLMP2クラス表彰台経験もある、若き実力派ドライバーでもある。予選やレース1では、誰よりもアグレッシブにスライドさせていたマイケル選手に、巧みにマシンをコントロールしていたことを訊ねると、「いやいやいや……」と、照れるシャイなところを見せたが、実際は「このクルマにはもう11年も乗っているからね」ということで、フォーミュラカーのコントロールに対する、絶大な自信をのぞかせていた。


ダグ・モケット選手は「我々アマチュアドライバーにとっては、プロフェッショナルために作られたマシンをドライブすることは、とてもチャレンジングで、うまく乗りこなすドライバーへの深い尊敬と、その技術への愛情すら感じるよ」と、マスターズF1の魅力をドライバー視点から語ってくれた。愛機のペンスキーPC4は、アメリカ製F1マシンとして勝利を修めた最期の車両にも関わらず、長年その行方が分からなくなっていた個体だ。それを約10年前にモケット選手が発見し、長い時間をかけて自らレストアして復活させたそうだ。こういったマシンを自分で修理することができるので、「だから思いっ切り走れるんだよ」とウインクしてくれた。約40年にも及ぶアマチュアレース経験の末に、マスターズF1の世界に辿り着いたという、ジェントルマンドライバーの鑑である。


レース2で「フィッティパルディ&スチュワート・クラス」で2位入賞のダニー・ベイカー選手は、レース2のオープニングラップで順位を落としたものの、レース中に順位を取り戻して総合8位、クラス2位をゲットした。初めて走ることになった鈴鹿については、「I love Suzuka! 素晴らしいトラックですよ」と、両手のリアクション付きで絶賛。嫌らしいコーナーが多いと言うドライバーもいるけど……と訊ねると、神妙な表情で「Yes。とてもテクニカルで、とても難しいコースだね」と答えてくれた。そして、一瞬の沈黙の後「ここを走らせるには『Big Ball』が必要だぞ!」と、笑いをくれることも忘れない。


レース2では、前日起きた駆動系トラブルで24号車ライアン選手がスタートできず、ペースの速い1号車パドモア選手がゴール目前でリタイアしたこともあり、34号車のヘンリー・フレッチャー選手がフィッティパルディ&スチュワート・クラスのトップでフィニッシュした。しかし、ドライバー間の絆が強いマスターズF1だけに、フレッチャー選手も複雑な表情だった。「I love Suzuka Circuit. ここは本当に素晴らしくて、これこそ本物のレーストラックだよ。近代的なグランプリ・トラックは個性に欠けている。ボクは狭くてアップダウンのあるコース……シルバーストーンやブランズ・ハッチで育っているから、鈴鹿はその点でもよく似ている。本物のコースであり、本物のドライバーズ・トラックだ。ここを走るには『覚悟』や『勇気』という言葉が必要になるくらいにね! 特に130R。ここはファンなコーナーだったね!」と熱く語ってくれた。


「なぜマスターズF1で走るのか」を訊ねたところ、ステファン・ロマック選手は「待ってました」とばかりに、「小さい頃に見ていたF1で、とても憧れていたクルマで実際に走ることができるからだね」と真っ先に答えてくれた。そして、「レースのスリルを味わえるし、マスターズF1シリーズは、ここ鈴鹿のように、歴史的なコースを訪れて走れるからだね」とも。年齢に合った一番若いマシンで戦っているだけに、レースファンの我々と何ら変わらない感覚であることがよく分かる。ロマック選手曰く、このレースはデモラン的な要素もあるが、彼自身はシリアスなレースとして走っているという。ただし、そのスタンスは、本気のレースから少しだけ引いたものであって、そこには車両の歴史的価値を守るという意味も含めて「little less」な立ち位置で挑んでいるとのこと。もちろん愛機ティレル012は、ロマック選手が幼少期に抱いた、憧れのマシンである。


マスターズF1シリーズの主宰であり、エントラントでもあるロン・メイドン選手。幻のマシン・LEC CRP1を持ち込み、レース1こそ走行したが、レース2では愛機マーチ741がトラブルで走れなくなったニック・コリバス選手にシートを譲って、主宰の立場に専念していた。これはマスターズF1の理念を体現する行為と感じたが、「さすがに厳格なFIAルールだと、こういうことはできないからね(笑)」と語る。気持ちとしては、自身がオーガナイズするマスターズF1の北米シリーズや、特別戦となる鈴鹿大会における、リラックスした運営方針を本当は大切にしたい様子だ。「次回も招待があれば喜んで来るよ。大会の後にパドックで行った表彰式では、参加したみんなの意思も確認したからね!」。