佐藤佑月樹選手が快挙! FIA Karting Academy TrophyのSenior 初代チャンピオン確定
2025年9月18日

佐藤佑月樹選手が今季のFIA Karting Academy Trophy - Senior(全3戦)のシリーズチャンピオンに確定した。カートレースにおいて、日本国籍のドライバーがFIA主催の国際的な大会で選手権/カップ/トロフィーのチャンピオンとなったのは、2021年にOKジュニアカテゴリーで世界選手権を制した中村紀庵ベルタ選手以来のことだ。その佐藤選手に、全日本カート選手権 OK部門の第5戦/第6戦決勝を2日後に控えたオートパラダイス御殿場(静岡県小山町)で話を聞いた。
FIA Karting Academy Trophyは、次代のカート界を担うドライバーを発掘・育成することを目的として2010年に始まったシリーズ戦で、OK/OKジュニアカテゴリーやKZ/KZ2カテゴリーのヨーロッパ選手権に併催してレースが行われている。参加選手は基本的に各国のASNから推薦を受けたドライバーで、2014年には太田格之進選手が日本人ドライバーとして唯一の優勝を記録している。
レースに使用するマシンはシャシー、エンジン、タイヤのすべてがワンメイクで、全車が現地の会場に用意されており、各選手にレンタルされる。さらにレーシングスーツも、同一デザインのものが各ドライバーに供与されている。
このレースは初年度から12~14歳のドライバーを対象に行われてきたのだが、今季はその範囲を拡大。新たに14~16歳のドライバーを対象とするSenior Academy Trophyが始まり、従来の12~14歳対象のレースはJunior Academy Trophyと呼ばれることになった。Senior Academy TrophyとJunior Academy Trophyは別の日程でシリーズが組まれている。佐藤選手はSenior Academy Trophyの初代チャンピオンに確定したわけだ。

2023年に全日本カート選手権 FS-125JAF部門でチャンピオンに輝き、すでに実績を挙げている佐藤選手が、このレースを目指したのはなぜなのだろう。
「2022年にROTAX MAX ChallengeのJunior MAXクラスでグランドファイナル(世界大会)に出たんですが、予選落ちしてしまって、すごく不甲斐ないと思ってめちゃくちゃ後悔したんです。それで今年Senior Academy Trophyが新設されることを知って、こんな機会はもう今しかないなと思って、すぐに応募しました」
「海外のカートレースはグランドファイナルが最初で最後なのかなと思っていたけれど、あのときからずっと背負っていた憎しみと苦しみを晴らす機会が来たんだ、という思いが応募のきっかけです。JAFから推薦をいただけると分かったときは、めちゃくちゃ喜びました」
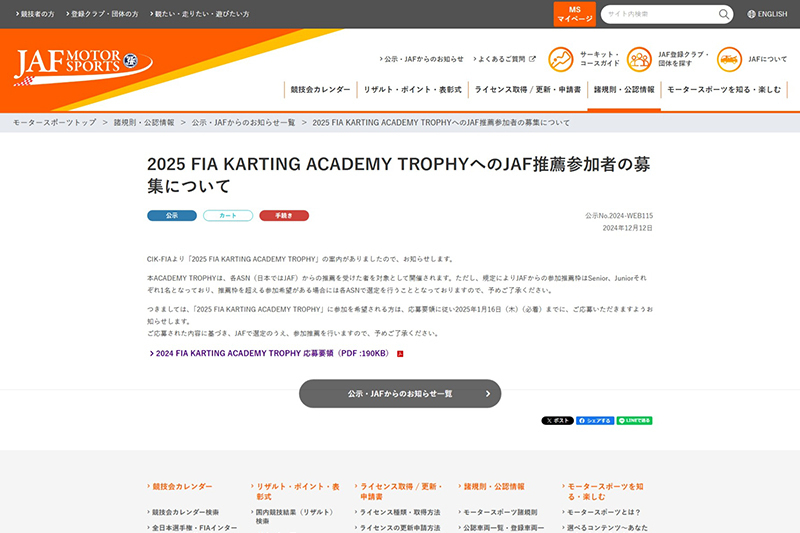
最初の大会は5月1~4日、ポルトガル・ポルティマオのアルガルヴェ・インターナショナル・サーキットで開催された。FIA Karting Academy Trophyは、日本ではまださほど実像が認知されていないレースなのだが、佐藤選手が初めて体験したそのレースはどんなものだったのだろうか。
「マシンはOK-Nカテゴリーで、排気バルブもないしキャブレターも調整ができません。スピード的にはX30エンジンのカートよりちょっと速いくらいですね。勝負は全部ドライバーの腕っていうことでセッティングも制限されていて、車高は下げられるんですけど、あとは何もできないみたいな感じでした」
「タイヤ(マキシス製)も路面もすごくグリップしますね。ちょっとステアリングを切っただけで、めちゃくちゃインリフトして簡単に曲がっていきます。逆に日本でレースしいてるときみたいにギュッて無理やり切っちゃうと、すぐガタガタガタって動きが乱れてしいます」
「メカニックは向こうの人で、すべてのレースで同じ人についてもらいました。ウクライナの人で、英語も全然喋れなくて、最初からイタリア語で急に喋るから、通じませんでした。同行してくれたお父さんや日本人のスタッフが通訳してくれてなんとかなりましたけど」

第1戦で佐藤選手はクオリファイングプラクティス(タイムトライアル)で3番手の好位置を獲得すると、3ヒートの予選で総合1番手となり、初戦にして決勝をポールからスタートすることに。その決勝はウェットから乾いていく路面コンディションの中で激しいバトルが展開され、佐藤選手は激闘の末にトップでゴールを遂げた。ただし、フィニッシュ間際のニアミスでペナルティを取られ、結果は3位だった。
「バトルとか頭脳に関しては向こうのドライバーの方が全然レベルが高くて、苦労しました。僕の今の状況だとやばいと思って、すぐ日本から同行してくれたスタッフの方にどうしたらいいですかって相談しました。Academyのレインタイヤはポルトガルで初めて履いたんですが、練習で急に3番手とかになって、このタイヤはもしかしたら自分に向いているんじゃないかなと思って結構自信がついて、メカさんと内圧の相談をずっと話していました」
「決勝のポールは奇跡というか、想定外でした。スタート前はめっちゃ緊張しましたが、逆にわくわくしてくるんですよ。他国のドライバーと戦ってると、やっぱり考え方とか全部違うじゃないですか。メカニックにリラックス、リラックスって肩を叩かれてちょっとリラックスできて、あとはもう自分とメカニックを信じて決勝に出ました」
「……最後は自分でぶち壊したんですけど。最終ラップにブロックしなければって、みんなに言われました。向こうの友達や友達のお父さんにも、速いのになんでブロックするんだとかめっちゃ言われて。自信がついたとも思えるけど、やっぱり一番は自分を恨んだレースでした」

第2戦は6月5~8日、イタリア・ヴィテルボのレオパード・サーキット・ヴィテルボで開催された。佐藤選手はクオリファイングプラクティス9番手、予選も総合9番手に。決勝ではそこからポジションを上げ、スタートのコリドー違反でペナルティを受けながら5位に入賞。これでポイントスタンディングのトップに立った。
「クオリファイングプラクティスが9番手で、ちょっとやばいなと思ったんですよ。きつかったですね。イタリアのコースってクオリファイングプラクティスが重要なんですよ。ミスっちゃうと下に埋もれてクラッシュに巻き込まれちゃう可能性が高いから。あれをミスらなければもっと行けたのかなと思います」
「決勝ではスタートの前にコリドーから出ちゃって、1周目から(ペナルティを告げる)フラッグが出てたから、これはもう駄目だと思って、それでもう飛ばして飛ばしてみたいなレースでした。それでチャンピオンシップリーダーになったんですよ。まだ勝ってもいないのに」

シリーズ最後の第3戦は7月31日~8月3日、デンマーク・ロドビーのロドビー・カートリングでのレースだ。ここで佐藤選手はクオリファイングプラクティス5番手から予選総合3番手に上がる。そしてウェットコンディションの決勝では、25周レースの8周目にトップに立って独走し、初優勝とチャンピオンをつかみ獲った。
「決勝に臨むときは緊張し過ぎて、スタート前のことはあんまり覚えてないんですよ。スタートして1、2周ぐらいは結構前と離れていたんですけど、絶対また追いつくだろうなと思って頑張って、相手のミスを狙ったりとかいろいろして、何とか前に出ることができました。そこから結構長くて、後ろからのプレッシャーも来るし」
「でも、勝ってチャンピオンなりたかったから、ずっと自分のペースをキープすることに集中していたら、7秒差をつけて勝っていました。やっと勝てたなと思って、しかもチャンピオンですごい気持ち良かったです。車検場でチームの人たちがめっちゃ喜んでくれて、OKジュニアの友達とかもすごく祝福してくれて、ありがたいなと思いました」

「全日本でFS-125JAF部門のチャンピオンを獲ったとは、チーム代表の金子雄一さんがチャンピオンにさせてくれました。金子さんにはカデットのときからずっとドライビングとかを教えてもらって、そこから今までが全部つながっているんだと思います」
「あと、Academy参戦に当たってJAFに推薦してくれた(所属チームであるYAMAHA MOTOR Formula Blue監督の)高木虎之介さんのおかげでもありますし、JAFの皆さんの推薦がなかったらAcademyには行けなかったわけですし、皆さんのおかげでチャンピオンを確定できたんだと思っています」

今回のチャンピオン確定で、ヨーロッパのカートメーカーやチームからの佐藤選手に対する注目度は一気に上がったことだろう。すでに限定Aライセンス受給の資格を取得しており、年齢的にはもう四輪レースに出場できる佐藤選手なのだが、2026年の活動予定では、国際カートレース参戦も視野に入ってきているのだろうか。
「僕の予定では、今年トヨタ(TGR-DCレーシングスクール)のオーディションに受かって、来年は日本でFIA-F4のレースに出て、1年目でちゃんと勝ってチャンピオンを獲って、その次はフォーミュラリージョナルに行くことになっているんです」
「でも時間があったらヨーロッパのカートレースにも1、2レースとか出ようかな、みたいなことを考えています。9月11~14日にスウェーデンのクリスチャンスタッドで開催される世界選手権(OK/OKジュニア)に僕もOKで出るんですが、最低でも予選落ちしないで決勝に行けたらなって考えています」

PHOTO/今村壮希[Souki IMAMURA]、長谷川拓司[Takuji HASEGAWA]、FIA Karting/KSP REPORT/水谷一夫[Kazuo MIZUTANI]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]



